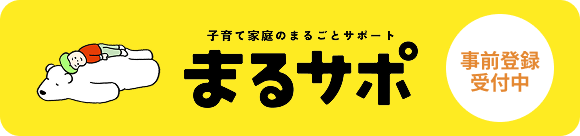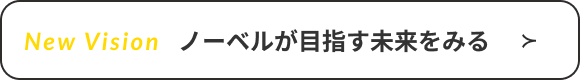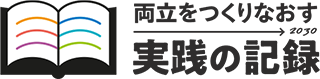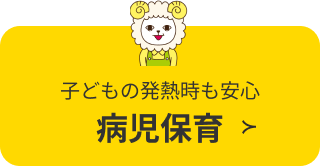(2025.07.03更新)
ノーベルと学ぶ保育
のぞき見!保育スタッフ研修|安心して子どもをひとりの人としてみるとは?
ノーベルでは、日々の保育の質を向上させ、より安心安全な保育を実施するために、保育スタッフ向けに専門的な研修を定期的に開催しています。リスクマネジメントや感染症予防、救命救急など多岐にわたるテーマの中でも、今回は先日実施された「人権研修」についてご紹介します!
今回の人権研修では、NPO法人えんぱわめんと堺の北野真由美先生と堀口博子先生にお越しいただき、「安心して子どもをひとりの人としてみるとは?」というテーマでご講演いただきました。
えんぱわめんと堺の北野先生は、20年以上にわたり、堺市内の小中学校で子どもの悩みや問題、そして人権についてワークショップ形式で活動されている専門家です。ノーベルでは毎年、「子どもの人権と性」など、子どもとの関わりにおいて大切な人権の観点を、参加型のワークショップ形式で楽しく学ばせていただいています。
今回もスタッフどうしのワークでは時折笑いもあり、実際に人権とはどういうことかを体感しながら学ぶことができました。
子どもとの関わりで「人権」が大切な理由とは?
「人権」と聞くと、「みんな仲良くね」「思いやりをもってね」といった言葉を思い浮かべるかもしれません。もちろんこれらは大切なことですが、人権は少し違います、と先生は仰られました。
人権とは、「人間が生まれながらに持っている、利益を主張できる権利」のこと。子どもたちも私たち大人と同じように、一人の人間としてこの権利をしっかりと持っています。
日本では2023年4月1日に「こども基本法」が施行されました。この法律は、子どもの権利条約に基づいて、「子どもを一人の人間として認め、自分らしく生きることを応援し、自己肯定感を高めること」を目指しています。このような社会の変化の中で、私たちは子どもたちとの関わりにおいて、これまで以上に人権の視点を持つ必要があります。
保育スタッフからは、子どもの権利条約について一度ちゃんと目を通しておきたいなど、前向きな意見が沢山あがりました。
子どもの「イヤ!」や「試し行動」は成長のサイン
子どもとの関わりの中で、「いや!」と言われたり、いわゆる「試し行動」をされたりすることもあるでしょう。つい頭ごなしに𠮟りたくなってしまうかもしれません。しかし、「試し行動」や「イヤイヤ期」は、子どもが自己主張し、自分自身を理解していくための大切な成長過程なんです。「いや」という意思表示を大切にする、受け止める、ということを何度も先生は仰っていました。
ワークではお互いに「いや」と言い合うことで、子どもが「いや!」と意思表示した時に私たち大人がどのように受け止めるべきか、「試し行動」の背景にある子どもの気持ちをどう理解するか、実践的に学ぶことができました。また、そんな時こそ、「あせらない」「あわてない」「あきらめない」の「3つの“あ”」で対応することが大切だと学びました。
「力関係」と「境界線」を意識する
また、人間関係には様々な「力関係」が存在します。特に、子どもと大人の間には、体力や知識、経験などの面で力の差がありますよね。この力の差を私たち大人が自覚し、「力で子どもをコントロールしていないか?」と常に振り返る意識が重要だと再認識しました。
さらに、人と人がお互いに心地よく過ごすためには、「バウンダリー(境界線)」の理解が不可欠です。境界線とは、「お互いが安全で心地よく過ごせるよう、自分と相手との間に引くライン」のこと。これは、自分にとっての「心地よい距離や空間」を指します。例えば、自分の身体、気持ち、持ち物、プライバシーなどが、それぞれの境界線に当たります。自分の境界線を守ると同時に、相手の境界線も尊重することで、より健全な関係を築いていけるのです。
具体的な保育のシチュエーションを想定し、境界線を可視化するワークを通して、この境界線の重要性を深く学ぶことができました。
受講した保育スタッフの声
今回の研修で、「人権」という概念をより深く理解し、子どもたち一人ひとりの個性を尊重しながら関わることの大切さを改めて学ぶことができました。
受講したスタッフからは、次のような感想が寄せられました。
子どもを一人の人として見る事の大切さを改めて感じた。知らず知らずに与えたり、受けている力関係をいつも振り返り考える事で良い関係、良い場、よい社会へと繋げていきたい。
子どもにとって、お菓子やおもちゃを自分で選ぶことも生きる力を育むための大切な過程なんだなと改めて感じた。普段の何気ない保育においても、そういったことを意識しながら、お子さんに声かけしたり、関わりを持つようにすることがお子さんの健やかな成長の一助になればと思う。
具体的なお話が多く、次の保育から「実践したい!」と思えるような内容だった。 今回の研修で知った対応を頭に入れ、実践していくことで身に付いていくのだろうと思うので、どんどん保育に取り入れていきたい。
普段無意識にしてしまっていることや考え方に一度踏みとどまって、今関わっているお子さんにとって最善の関わり方はどうなのかを考えていきたいなと思いました。
子ども自身が自分を大事な存在だと感じられるように相手を尊重することがとても大事だと思った。
ノーベルでは、このような専門的な研修を通して、保育スタッフ一人ひとりが日々スキルアップに励んでいます。保育スタッフは今回も熱心に話を聞き、日々の保育に活かせることはないか、前向きに考えて研修に臨んでいました。そうした研修を重ねるなかで、日々の保育の質も高くなり、利用者さまとの信頼関係につながっているのだと感じます。
また、ノーベルでは入職前からノーベルスタッフと一緒に研修を受けられる制度「ノーベルさんのたまご」もあります。
保育のお仕事をしてみたい方、研修に参加してみたい方、ノーベルに少しでもご興味のある方はぜひお気軽にお問合せください。ご応募お待ちしています!
RELATED POSTS

保育者として働く

保育者として働く

保育者として働く